MAM
(マム・非営利・一般社団法人)
映像シリーズ『ニッポン・コンシェルジュ/イタリア人が案内するニッポン』の企画・制作。
ジャズ作曲家、挟間美帆、CD制作助成。
音楽家、綱守将平、CD・コンサート制作助成。
音楽プロデューサー、牧村憲一によるコンサート、レクチャー・シリーズの制作。
概要
MAM (マム・非営利・一般社団法人)
- 主たる事務所
- 東京都品川区
- 活動期間
- 2012年〜
- 代表理事
- マスヤマコム
MAM(マム)は、マスヤマコム(桝山寛)を代表理事とする、非営利型・一般社団法人で、音楽・アート・文化学術・科学技術などへの助成、コンサート、レクチャー、アート展、映像などを自社で企画し、制作する非営利事業を行っている。
お知らせ
これまでの活動
過去の活動
理事・監事
代表理事 桝山 寛
理事 飯塚 優子
理事 黒澤 一夫
理事 坂井 幸彦
理事 中部 由郎
理事 八谷 和彦
理事 桝山 雄三郎
監事 小山 隆史
監事 杉谷 卓志
ミッション
MAMのミッション
Music
音楽は、人々の気持ちを同期させることができる時間芸術である。
価値観が多様化する時代に、音楽のその役割を最大限活かすことで、人と人の相互理解を促進する。
Art
アートは、人間特有の「シンボル化能力」を活用する視覚芸術である。
人の想像力をシンボル操作によって視覚化し、「美」に対する新たな価値を模索する。
Media
メディアは、人と人の情報共有を可能にする道具である。
人間関係の集合体であるところの「社会」の秩序を維持するために、メディア技術及び科学の活用を推進する。
公告
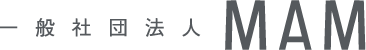


 ジャズ作曲家、挾間美帆、CD制作助成
ジャズ作曲家、挾間美帆、CD制作助成
 音楽家、網守将平、CD・コンサート制作助成
音楽家、網守将平、CD・コンサート制作助成
 音楽プロデューサー、牧村憲一によるコンサート、レクチャー・シリーズの制作
音楽プロデューサー、牧村憲一によるコンサート、レクチャー・シリーズの制作
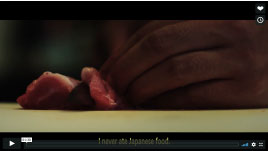 和食を世界各地の子供に食べてもらうショート・ムービー“オマカセ・フォー・キッズ”の制作
和食を世界各地の子供に食べてもらうショート・ムービー“オマカセ・フォー・キッズ”の制作