2018.12.19 17:53
Text by Masu Masuyama 文・写真:マスヤマコム
音楽ストリーミングサービスSpotiyで、2018年にもっとも聴かれたアーティスト(個人)のうち、4人がラッパーであり、2人は中南米出身でいわゆるラテン的なリズムの曲がヘビロテされたことになる。同時代のポップ・ミュージックに少しでも興味がある人なら、アーティスト名や曲名は知らなくても、この辺の曲は耳にしているだろう。
事前に強調しておくが、ここで書く「訛り」というのは「正しい発音やイントネーション」がどこかにあって、それに対する「正統的でない発音やイントネーション」という意味ではない。音階が「ヨーロッパ古典音楽」で使われてきた「ドレミファソラシド(など)」が正しくて、ジャズやブルースで使われる音階が正しくない、というわけではないように、だ。むしろ、ジャズやブルースは、「ドレミファソラシド(など)」ではない音階を楽しむ音楽、という言い方さえできるかもしれない。それを「訛り」を楽しむ、と言い換えてみたらどうだろう?
初期のYMOは、それまで人間の演奏による「グルーヴ感」や「ノリ」を追求してきた手練れのミュージシャンが、コンピュータ(シークエンサー)に音楽を演奏させることで「グルーヴのないリズム」のおもしろさに目覚め、それを追求していたという。もちろん、彼らはアーティストでもあるので、その「グルーヴのないリズム」がわかってしまうと、次には「機械・数値的な計算でグルーヴを作り出す」というメタレベルな音楽制作に入っていった。これを、計算で「訛り」を作り出す、としてみたらどうだろう?
20世紀のポップ・ミュージックは、言うまでもなくアフリカン・アメリカンが持っている「ヨーロッパ古典的ではない」ビート感や音階感に依拠している。冒頭のSpotifyランキングでも、人種や国籍を問わず、アフリカン・アメリカン的なビート感の楽曲が大ヒットしているのがわかる。中でもラップは「訛り」そのものを楽しむ度合いが高いのではないか?
Spotiyのランキングに戻ろう。もうひとつの特徴「ラテン」だが、エド・シーランもジャスティン・ビーバーも「ラテン」的なビート感の大ヒット曲をもっている(ビーバーの楽曲は2015年)。そしてこれは、定量的なデータではなく、年に数ヶ月は海外に居る私の極私的感触だが、世界じゅうで、ある程度自由にポップ・ミュージックが聴ける文化圏において(日本を除く!)は、「ラテンとラップがかかりまくっている」というのが率直な印象だ。ロックの8ビートからすれば、どちらも「訛っている」と言えなくもない…。
「訛りを楽しむ」のは、もちろん、音楽だけではない。日本で「お笑い」といえば「関西弁」が大きな勢力だし、方言をうまく使って人気が出るタレントも少なくない。もう5年以上前の話になるが、朝ドラの『あまちゃん』では岩手の方言が、確実に魅力にひとつになっていた。手前味噌だが、私が製作代表の一人に入っているアニメ映画『この世界の片隅に』も、(パフュームのライブでのトークも!)広島弁が楽しい。
ラップ、ラテン、そしてK-pop(さらに言えば数年前の”PPAP”)。ローカルな特徴(訛り?!)を持った音楽が、グローバルに大ヒットする。この傾向は、当分続くに違いない。
====
本文ここまで、です。ツカサくん筆の『訛り』から思いついて、ちょっと転がしてみました。「そんなこと、とっくに知ってるよ!」という方も居るかもしれませんが、訛り感の強い楽曲と、訛り感の少ないEDM。ポップ・ミュージックの世界では、その両極の人気がはっきりしているように思います。
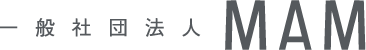

 ジャズ作曲家、挾間美帆、CD制作助成
ジャズ作曲家、挾間美帆、CD制作助成
 音楽家、網守将平、CD・コンサート制作助成
音楽家、網守将平、CD・コンサート制作助成
 音楽プロデューサー、牧村憲一によるコンサート、レクチャー・シリーズの制作
音楽プロデューサー、牧村憲一によるコンサート、レクチャー・シリーズの制作
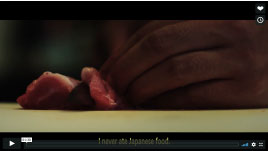 和食を世界各地の子供に食べてもらうショート・ムービー“オマカセ・フォー・キッズ”の制作
和食を世界各地の子供に食べてもらうショート・ムービー“オマカセ・フォー・キッズ”の制作